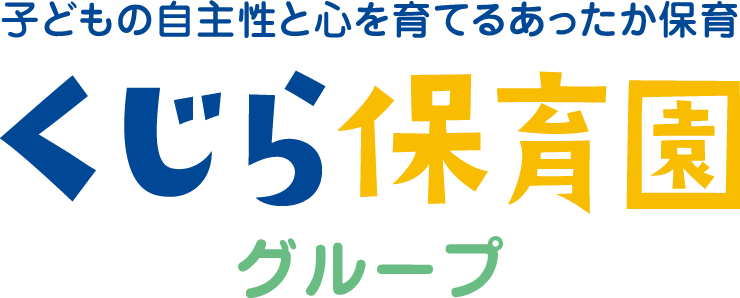グループの特徴
くじら保育園グループの5つの強み
私たちの保育園グループは、子どもたちの健やかな成長と、保護者・地域との信頼関係を大切にしながら、5つの柱を中心に保育の質を高めています。
1. 研修

保育の専門性を高めるため、定期的な研修を全園で実施。新人からベテランまで、学び続ける姿勢を大切にし、保育の質をグループ全体で底上げしています。
2. 食育・給食

「食べることは生きること」。季節の食材を使った給食や、プランターでの栽培体験などを通じて、子どもたちが食への関心を育み、感謝の気持ちを持てるような取り組みを行っています。
3. 保護者支援

子育ては一人ではできません。保護者の悩みに寄り添い、相談しやすい環境づくりを心がけています。園だよりや面談、イベントなどを通じて、保護者との信頼関係を築いています。
4. チームワーク

職員同士の連携が、子どもたちの安心につながります。日々の情報共有や、園を越えた交流を通じて、グループ全体で支え合う文化を育んでいます。
5. 異年齢保育

年齢の違う子どもたちが共に過ごすことで、思いやりや社会性が自然と育まれます。年上の子が年下の子を助ける姿は、保育の中で最も美しい瞬間のひとつです。