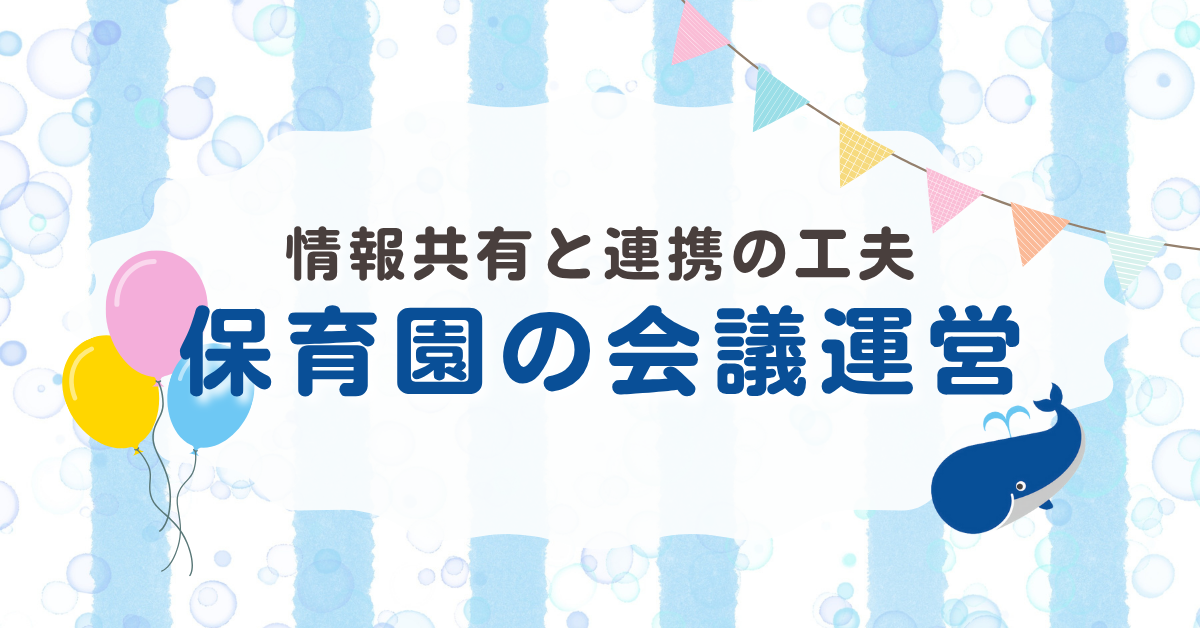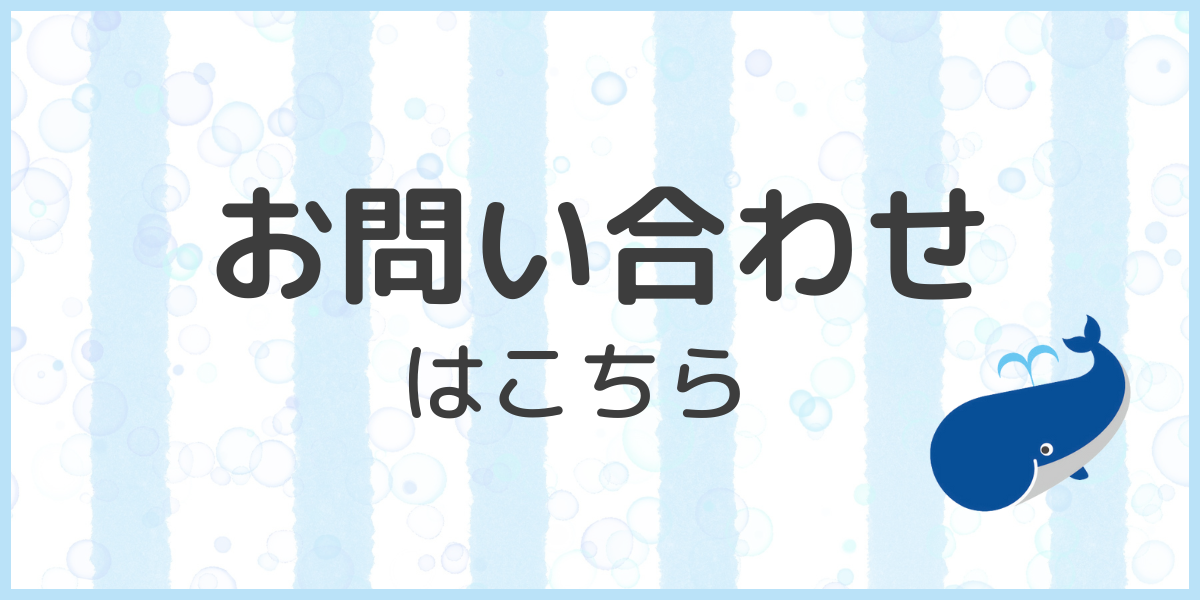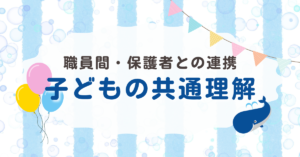子どもの共通理解|職員間・保護者との連携
東野田園では、子どもたち一人ひとりの個性を大切にしながら、職員全員で共通の理解をもって保育にあたることを大切にしています。
ここでは、「子どもの共通理解」をテーマに、職員間の取り組みやその重要性についてご紹介します。
子どもの共通理解とは

「子どもの共通理解」とは、複数の保育士が同じ子どもに対して同じ認識を持ち、関わり方や援助の方法を一貫して行うことです。
一人ひとりの子どもの育ちや個性を一貫した姿勢、適切な援助を行うことで、職員間だけでなく、保護者とも連携して子どもの姿を共有することで、子どもはより安心して安定した園生活を送れるように環境にしていきます。
子どもの共通理解が重要である理由
① 子どもの安心感につながる

複数の保育士が同じ認識で関わることで、子どもは誰が相手でも安心して過ごせます。
関わり方に違いがあると、子どもは混乱して落ち着きをなくしてしまうことがあります。
担任が丁寧に関わることで愛着関係が生まれ、安心した日々を送ることができます。
② 保育の質の向上につながる

一人ひとりの子どもを深く理解することは保育の出発点です。
共通理解があることで、保育者は子どもの成長を促すための環境設定や声かけをより適切に行うことができます。

東野田園では週1回、担任が集まり自己反省会を行い、次週の保育に活かしています。
③ 職員間のチームワークが深まる

保育観や活動目的を共有することで、職員は同じ方向を向いて連携を強化できます。
日々の振り返りや話し合いを通じて相互理解が深まり、チームとしての結束力が高まります。

東野田園は、週1回は週案会議を行い
各クラスの活動状況や子どもの様子を共有し週案を立てていきます。
子どもたちの共有は日々、行っております。
共通理解を深めるための取り組み
職員間での情報共有

- 日々の口頭での情報共有: 連絡帳に書ききれない、その日の具体的なエピソードや変化について、休憩中や登園・降園時にこまめに伝達します。
- 定期的な話し合いの場を設ける: クラスごとの課題や子どもの様子について、じっくりと話し合う機会を作ります。
- 共通の記録ツールを活用する: 連絡帳や日誌だけでなく、クラス全体の子どもの様子がわかる記録ツールなどを活用し、視覚的に情報を共有します。
- 保育観を共有する: 園の理念や保育方針について研修で話し合い、抽象的な言葉ではなく具体的なエピソードを交えて共通認識を深めます。
保護者との連携

- 何気ない日常の様子を伝える: 連絡帳や送迎時の会話で、子どもの普段の様子を具体的に伝えることで、保護者との信頼を築きます。
- クラス懇談会や個人面談を行う: 定期的な面談や懇談会で、子どもの成長を具体的に伝えたり、家庭での様子を尋ねたりする機会を設けます。
- 園での活動の成果を共有する: 写真や動画、作品展示などを通して、園での子どもの様子を保護者と共有します。


東野田園のチーム保育と職員の雰囲気
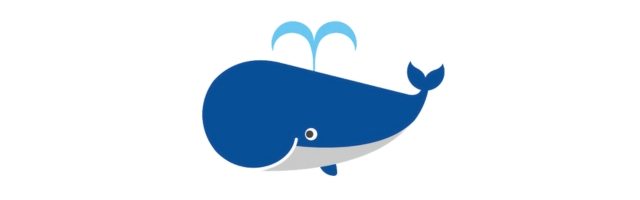
東野田園では、20代から50代まで幅広い年齢層の職員12名(うち調理員2名)が働いています。
職員同士は、とても仲が良く離職もなく産休・育休を取得してまた園に復帰してもらえる温かな雰囲気も自慢の一つです。職員の個性溢れる雰囲気の中、子ども達の感性や主観を大切に一人ひとりに寄り添い保育が行えるように日々共有は大切にしております。
見学に来ていただいた保護者の方からは、アットホームな雰囲気で温かさをとても感じられるとお褒めの言葉をいただきます。
子ども達の園生活の可愛い姿やエピソードを、毎日保護者方に共有させていただいています。
日々の保育の中でも職員のチームプレーが重要であり、「子どもの共通理解」はとても大切です。
日々職員が話し合うことで、より一人ひとりに寄り添った丁寧な保育ができるよう、今後努めていきたいと思います。